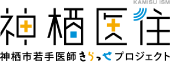神栖市では、「魅力ある 誇れる 神栖市を目指して」をまちづくりの将来像として施策を推進しています。その主要な取組のひとつとして「神栖市若手医師きらっせプロジェクト」に取り組んでいます。「きらっせ」とは「どうぞお越しください」と親しみを込めた方言です。
本市は、大海原を臨む太平洋、澄み切った広い空、悠久の流れを湛える利根川に囲まれ、いにしえから全国各地と行き交ってまいりました。息栖神社は、鹿島神宮、香取神宮とともに古くから「東国三社詣」として賑わう拠点であり、歴史的な交流文化を誇っております。
現在は、盛んな農業や水産業、水産加工業の特産品が全国にお届けされています。鹿島アントラーズのホームタウンでもあり、官民合わせて100面を超すサッカー場を有する当市は、サッカー合宿の聖地として、また、プロスポーツの拠点として、年間約30万人の方にお越しいただいています。鹿島臨海工業地帯の中心地として170社を超える企業が立地し、年間約1,800隻もの外国船が行き交う、国際的な工業都市であります。医薬品の原料製造などを行っている企業も多く、医療を支える工業地帯でもあるのです。
このように様々な分野での交流が盛んで、人口の流出入も多く、コロナ禍前まで人口が増え続けておりました。直近の合計特殊出生率は県内市町村で1位です。まさに多様な主体が、互いに「きらっせ」という思いを大切にしているふれあいのまちであります。

私は、平成29年12月の市長就任以来、医療体制の整備を主要政策の一丁目1番地として位置づけ、様々な取り組みに挑んでまいりました。
緊急医療対策チームの設置による救急医療体制の整備に着手し、一刻を争う循環器疾患救急患者受け入れのためのホットラインの設置や当番表の作成をスタートしていただきました。
令和元年度には、茨城県立中央病院の名誉院長である永井秀雄先生のご助力をいただき、神栖市地域医療体制検討委員会を設置しました。市内外の有識者の参画の下で、鹿島労災病院と神栖済生会病院の再編統合を踏まえつつ、将来の神栖市が目指す医療体制整備の方向性として9つの分野の提言をいただきました。
提言の中で最も気配りが大切なのは、「市民の方々の不安解消のために重要なことは直面する課題やそれに対する取組などの実情を飾らずに正確に情報提供すること、そして、医療資源が脆弱であるからこそ、市民や企業の皆さんの理解と賛同を得て、様々な立場のみなさんの力を結集していくことが必要であること」と認識しております。
市政運営において最も心がけていることは、いかなる分野においても、様々な立場の利害や課題を受け止め、皆さんのベクトルを一致させる努力を惜しまないことです。市長としての私の政治姿勢とこの提言はぴったりと一致します。
そこで、医療の情報提供にあたっては、このような認識の下で、医療を提供する側と受ける側が、双方向のやり取りを通じて相互理解が深まるよう、直接間接の情報交換の機会を持てるよう工夫しております。いずれの医療対策にあたっても、ひとりよがりにならないよう、市内外の大勢の皆さんのご意見をうかがいながら、地道に取り組むよう心がけています。
令和元年度に、永井秀雄先生にコーディネーターに就いていただき、「神栖市若手医師きらっせプロジェクト」を発足しました。市内医療機関の指導医の皆さんとともに、指導医や研修医の皆さんが、ともに学び、働き、活躍する体制づくりのチャレンジを始めました。もとより、各医療機関の教育研修環境づくりや魅力づくりは、個々に自助努力すべきことが前提です。一方で、限られた医療資源や体制の中で、医療機関が力を合わせたり、行政と連携協働することで、単体では取り組めない魅力づくりや情報発信が可能になるのではないか、といった視点から取り組んだものです。
このプロジェクトは、スタートから6年が経過しました。市民や企業の皆さんのご協力が得られたり、市内外の医療機関、医療人、医科大学などのネットワークの広がりや強化、医学生をはじめ立場の違いを超えた皆さんの力添えをいただくことができました。成長を実感しております。

プロジェクトの事業の中で、特に力を入れたのは、地域特性を生かした研修メニューの創出です。
私たちは、まずはじめに、産業都市ならではの優秀な産業医の存在に注目しました。産業医の皆さんも、当地での産業医の育成に意欲をお持ちでした。そこで、茨城県医師会にご理解をいただき、当市を会場に産業医学基礎研修会を開催できることになりました。これまでに、全国から延べ4,000人以上の方々に当市に訪れていただいており、当市のアピールにもつながっていると思います。また、白十字総合病院や神栖済生会病院、行政、指導に当たる産業医の連携により、産業医の実務能力の養成や社会医学系専門医を取得する神栖産業医トレーニングセンターが創設されました。全国から若手医師がたくさん就業してくれています。そして何よりも、私どもプロジェクトメンバーの地道な取り組みをご理解くださり、企業の皆さんが、休日にボランティアで産業医学基礎研修会の実地研修フィールドとして、工場での受け入れをしてくれています。日本の他地域にはない、リアルな実地研修機会を提供しているのです。企業の皆さんに心から感謝すると同時に、こうした企業との連携実現をとても誇らしく思っています。
次に、企業の皆さんと医療について意見交換する場として、企業・医療機関・行政連絡調整会議を設置しました。企業の皆さんから、労働災害の市内受け入れ体制の強化が要望されました。特に、コンビナート工場ならではの熱傷や薬傷の救急対応が課題として浮かびあがりました。市内医療機関や消防本部との救急医療ワーキングチーム会議の中で、市内ドクターから、熱傷や薬傷の症例を勉強し、まずは軽傷なら専門医でなくとも診療できるようにしようと提案がありました。これを受け、このプロジェクトの研修メニューとして、救急搬送先の医師や国内の専門家を講師にお迎えし、症例検討会を開始しました。市内医療機関の医師、看護師、コメディカル、そして企業の担当スタッフの皆さんが参加しての検討会も5回を数えております。工業地帯ならではの検討会として継続し、発展させていきたいと考えております。
さらに、いまはプロジェクト分科会の中で、農業や漁業、工場群、往来する外国船乗組員などの多数の外国人への医療提供について議論しています。適切な医療サービスの提供に加え、トラブル防止などの円滑な対応への備えが課題となっていることから、この事案についても、研修メニューとしてラインナップに加えていく方向で取り組んでいます。
プロジェクト推進会議の中で、市内に勤務する若手医師の中から、児童生徒への医療教育を実施したいとの意欲が示されました。コーディネーターの永井先生は、医療教育に造詣が深いこともあり、永井先生のご指導をいただきながら、その実現を検討いたしました。当市の医療教育は、医療人の出前講座とは別性格のものです。小中学校の教諭と医療側の医師、看護師、助産師、保健師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士などが一堂に会し、授業を検討します。医療側は、まず学習指導要領と教科書を熟読します。そして、専門家としての知見を加えたカリキュラムを考案します。授業の進め方や留意点についは、プロである教諭から気づきの与え方から振り返りの方法、扱う情報の適否などを指導いただくほか、本人や家族に疾患を抱えていたり、メンタルが不安定な状態である児童や生徒への個別対応、配慮すべき視点などを共有します。そのうえで、医療人がおもいっきり授業にチャレンジします。病院の外でのこうした機会も、神栖市で働く医療人のやりがいに寄与できているのではないかと思っています。
令和6年10月には、当プロジェクトと地方創生医師団との共催により、当市で地域医療シンポジウムを開催しました。大勢の市民の方々に、当市を訪れた医学生や社会人の方々への市紹介のアテンド役を務めていただくともに、シンポジウムの討論にご参加いただきました。もとより、当市では、医療体制づくりへ、市民や企業の参加と協力をお願いしてきているところでありました。シンポジウムでは、「地域医療を志す者を育て、励まし、鍛えるのは市民であることを再認識しよう。」「市民、医療機関、行政、学生、指導者は、地域医療を志す者が学び、働き、活躍するフィールドづくりに全力を尽くそう。」そして、当プロジェクトでは、「地域に隠れている様々な思いを、具体的でポジティブな力に変えて発信していこう。」という神栖宣言が採択されました。当プロジェクトへの新しい宿題だと受け止めています。
令和6年7月には、神栖市独自の医師修学資金貸与制度を利用してくれた第1号医師が市内で勤務を開始してくれました。
現在、国内外の医科大学で学ぶ医学生や卒業生を応援しております。神栖市と縁を結んでくれた若手ホープには、将来神栖で働くことをわくわくと待ちわびてくれるような環境づくりが何よりも大切であると認識しています。
プロジェクトの大事なミッションは、市内で頑張ってくれる医師を十分にサポートし、大きく成長してもらい、そして、神栖で働いてよかったと満足してもらえるようにすることだと思っています。地域の方々との連携・協働の機会は、ひとりでにできるものではなく、多くの主体の理解と賛同、参加と協力の地道な積み重ねでできるものです。それを存分に味わえるフィールドがここにはあります。他地域にはない、当市の地域医療の醍醐味の一つだと思います。
どうぞ、神栖市に「きらっせ」