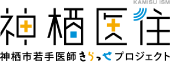医師になって50年以上経ちます。都会の病院で1年間の研修のあと、地方の病院に出ました。私が専門としてきた肝胆膵外科の基礎はそこで習得しました。指導医・先輩から教わったことも多くありましたが、自分から進んで学び取ったことも少なくありませんでした。
都会の病院と違って、地方に出るとさまざまな病態・疾病の患者を一定程度自分で診なければなりません。専門医が全て揃っているわけではないからです。どうしても自分の守備範囲を広げなければなりません。外科部長の許可をもらい飛行機に乗って経皮経肝的胆管造影(PTC)を学びに行きました。病院長の計らいでEPCG(今のERCP)用の内視鏡を買ってもらいました。地方では患者と医療者との関係が都会よりも濃密です。丁寧に診察していると患者がどんどん増えていきました。閉塞性黄疸患者が次々私の受け持ちになりました。残念ながらPTC/EPCGで診断した閉塞性黄疸は進行した膵臓癌ばかりでした。全ての患者を自分が担当し、全ての患者の最期を見送るうちに切除可能な遠位胆管癌を遂に見つけました。卒後2年4か月で膵頭十二指腸切除の術者となりました。手術は外科部長の指導で無事終了し術後合併症もなく退院しました。私が離任するまで元気に外来に通っていました。もちろん、今は昔と違います。地方にいても情報はすぐに入りますし、インターネットを利用すれば勉強の機会は格段に増えます。それでも地方で学ぶ意義は変わっていないと思います。新しい土地での新たな出会い、患者とその家族との濃密な関係、さらに豊かな自然があれば、医師人生の一時期を過ごす絶好の場となります。

私が茨城県神栖市を初めて訪れたのは地方から都会の大学病院に戻って1年後、卒後6年目のことでした。大学の先輩が入院したので手伝うようにと医局長に言われたのが、旧 波崎町(現 神栖市)の医院でした。1か月間、医院の2階に住み込んで診療にあたりました。午前は外来、午後は往診でした。浜風の吹く海沿いや畑の中の家を訪ねて回りました。早朝、臨終の場に呼ばれたことがあります。開け放たれた広い和室の真ん中に上品な布団が敷かれ、女性のお年寄りが目を閉じて静かに伏せていました。周りには十人ほどの家族や親戚が正座していました。小学生の姿もみられました。すでに身体は冷たく、夜が明けるのを待って医師を呼んだことが分かります。脈と瞳孔を拝見し聴診器を胸に当てたあと、ご臨終を伝えました。「ありがとうございます」。声をそろえ、私に向かって一斉にお辞儀をしました。看取りの原点が代々伝わっていく大切さを思わずにいられませんでした。
こうした光景はもう見られないかもしれません。それでも似た場面は今もあるはずです。
茨城県外のいくつかの病院勤務を経て、59歳のとき茨城県笠間市にある茨城県立中央病院に赴任しました。自分の病院の診療を維持しさらに向上させる努力をしましたが、県職員としては同時に、医療資源の乏しい県北部や県西部、鹿行(鉾田・鹿嶋・行方・潮来・神栖)地域の医療を真剣に考えました。それは、医療のあり方を根源的に考えることでもありました。若手医療者の教育と支援、専門性と総合性、多職種間連携、施設間連携、市民/県民への医療教育の重要性に気づき、共感者とともにさまざまな取り組みをしてきました。
痛感したのは、医療者と市民/県民だけでは良い医療の達成は困難であるということでした。どうしても行政と政治の支援がないと難しいということでした。もちろん、自分の日々の診療の満足度は高いものでした。地方での医療の醍醐味は十分味わえました。しかし、医療資源の乏しい地域の医療への支援は限界がありました。

60歳代半ばで退官を迎え、名誉職に就いてしばらく経ったころ、神栖市から「若手医師きらっせプロジェクト」の話がありました。人口当たり医師数では茨城県は全国ワースト2、その茨城県の人口当たり医師数のさらに半分しかないのが鹿行地域です。そこに若手医師・医療者を呼び込もうという企画です。行政がこれほど熱心に若手医療者を育成しようという試みを知りませんでした。表層的ではなく、多重性・深層性のある支援が継続されています。さらに、市民が地域医療を理解し、若手医療職の育成にも協力する姿勢に共感を覚え、「若手医師きらっせプロジェクト」のコーディネータを引き受けました。その後、医師を含め多くの医療者が神栖に集まるようになりました。
2024年10月、神栖市は地方創生医師団(TAO)との共催で「地域医療シンポジウム」を開き、「地域医療を志す者を育て、励まし、鍛えるのは市民であることを再認識しよう」という神栖宣言を出しました。市民を巻き込むという画期的な宣言です。
医療資源の乏しさを嘆くばかりでは成果を上げることはできません。神栖市はその先を行こうとしています。市民が一緒になって医療を支える文化がこの地域に間違いなく育ってきていることを嬉しく思っています。